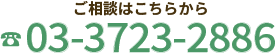漢方診療の口訣(くけつ)とは? 処方までの流れは?
■診察前(又は診察中)から有効な漢方薬を推測できることはよくあること
今までのコラムで何度も説明していますが、
漢方診療で処方薬を決める場合、詳しく診察する必要があります。
症状や病名から処方する漢方薬を決めるのは間違っており、この処方方法は漢方内科以外で多いようです。
例えば詳しく診察をしないで
「(西洋薬の他に)漢方薬もあるので処方しておきますね」
「漢方薬もあるので飲んでみますか?」
「この漢方薬が良いと思います」
というような流れで漢方薬を処方されたら、たとえ有効であったとしても間違った処方方法です。
漢方診療の経験を積み重ねていくと、詳しく診察する前に
患者さんの症状・外見・声の様子などから、
「漢方薬○○が効きそうだ」と頭に思い浮かぶことはしばしばあります。
漢方処方の場合詳しく診察して「証」を診断しますが、
患者さんの「証」を詳しく診察する前から推測できる、
ということはしばしばあるのです。
この時点で処方する漢方薬を決めたら症状処方・病名処方になるので、漢方内科ではそのようなことはもちろんしません。
有効そうな漢方薬が思い浮かんだ場合、その漢方薬で矛盾がないか、詳しい診察をして確認してから最終的な処方を決めるのです。
■漢方診療の口訣(くけつ)とは
漢方の名医の先輩方は、
患者さんの症状や状態などからどの漢方薬が効きそうか、
(診察する前から又は診察中に)経験則で頭に思い浮かぶことが多く、
それを弟子たちに格言・秘伝のようなものとして伝えていました。
このような格言・秘伝を
紙に文字で書いて残さずに口頭で伝えた場合、それを
口訣(くけつ)
と言っていました。
■おそらく漢方医は皆独自の口訣がある
一般的に言う口訣は、
弟子にだけ教え、かつ紙に残さないものだったので
企業秘密のようになっていた可能性もあります。
でも、紙に残されて公表されている口訣もあるので、
実際は
経験則で有効な漢方薬を推測できること=口訣
としてとらえられているようです。
今回説明する口訣は、
「紙に残すか残さないか」「弟子たちに秘伝として伝えるか伝えないか」
は無関係とし、
「経験則で診察前又は診察中に有効な漢方薬を推測できる場合」
のことを口訣とします。
そのため、本来の口訣の意味合いとは少し違うかもしれません。
あくまでも経験則で推測できる漢方薬を発見したらそれを「口訣」と呼ぶということです。
漢方診療を多く積み重ねている先生方は、おそらく先生方独特の口訣が増えていると思います。
たくさんの漢方診療をすることで、
「こういう場合にこの漢方薬が効きそう」
という発見が増えていく、つまり口訣が自然と増えていくものなのです。
自身も本に書いていないような内容で、この状態ならこの漢方薬が効きそうだ、というような独自の口訣が少しずつ増えています。
■口訣は患者さんが教えてくれて増えていく
前述しましたが漢方診療する際、必ず「証」という漢方医学的な全身状態を診断してから処方薬を決めます。
くどいようですが、西洋診療のように症状や病名から処方薬を決めるのではありません。
漢方診療を積み重ねていくことで、ある症状や状態から共通の「証」の人が多いことに気づくことは多々あり、それが本に書いていないことだと、それを発見した先生の一つの口訣と言えると思います。
独自の口訣は、漢方診療を積み重ねていくことで色々な患者さんから医師が学んで増えていくものだと思います。
これは、本で勉強するだけでは得られないものなのです。
■最終的には必ず証を診断する必要がある
繰り返しますが、口訣から漢方薬を直結して決めることは、漢方内科ではしません。
直結させたら証を診断する前に処方を決めてしまうことになり、いわゆる病名処方になってしまうからです。
実際に診察すると、口訣の漢方薬が最善の漢方薬でないこともあるのです。
そのため、詳しく診断して証を診断してから処方を決めることは必須なのです。
■処方を決めるまでの流れの一例
おそらくほとんどの漢方医は次のようにして処方を決めていると思います。
① 症状や状態を確認する
② (①の内容から)いくつかの漢方薬が口訣として頭に思い浮かぶ
③ 詳しく診察をする(腹診など)
④―⑴
最初に思い浮かんだ漢方薬の候補のうち「証」にぴったりの漢方薬があればそれに決定(口訣通りだったということはあります)
④―⑵
最初に思い浮かんだ漢方薬のうちぴったりの漢方薬がない場合、その中で一番矛盾が少ない漢方薬を処方する(矛盾は少なからずあることが多いです)。
万が一その漢方薬が有効でない場合は再診時に第2候補だった漢方薬を処方する。または「証」を再考して違う漢方薬を処方する。
④―⑶
詳しい診察をした結果、最初に思い浮かんだ(口訣で思い浮かんだ)漢方薬はどれも違うと気づき、別の漢方薬の「証」だと分かりそれを処方する
口訣ですぐ処方を決めてはいけない理由は、上記④ー⑶の場合があるからです。
つまり口訣は絶対ではないので、詳しい診察は必須だということです。
新たな口訣を発見できると、漢方診療はとても楽しくなります。